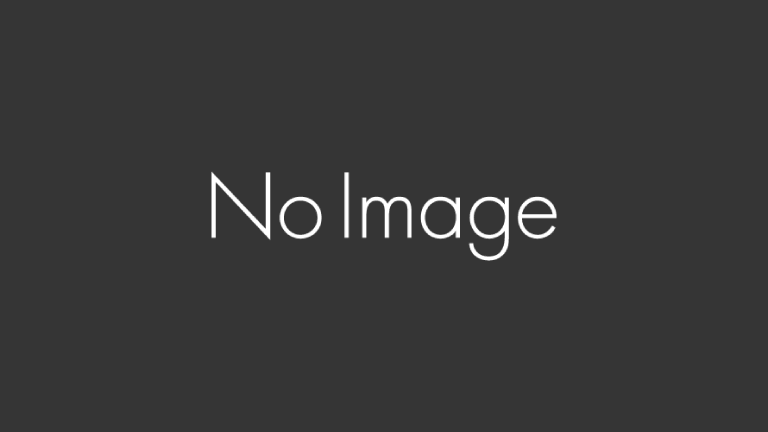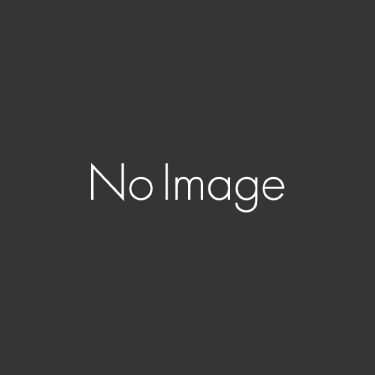「柔よく剛を制す」は実現するか
本ブログは、柔道に興味のある〜初段取得程度までの方を対象に書いている。
柔道への理解と競技人口増加の一助となってくれれば幸いである。
今回は其の壱ということで、柔道でよくイメージされる有名なワードについて書いていく。
最もよくイメージするワードの一つとして「柔よく剛を制す」というものがあるだろう。
正に柔道を象徴するような表現で、誰もが一度は耳にしたことがあるのではないだろうか。
まずは、柔よく剛を制すの持つ一般的なイメージを書いてみる。
- 力の弱いものが力の強いものを倒す
- 体の小さいものが体の大きいものを倒す
ざっくり書いたが、こんな感じではないだろうか。
確かに少年漫画でよくありそうなシチュエーションではある。
しかしながら、現実はとても過酷であり、まったく存在しないわけではないが、そうそうお目にかかることはない。
こと柔道においては基本的に力の強いものが勝ち、体重の大きいものが有利である。
最初からまったく夢のない話で申し訳ない気持ちもあるが、これは物理法則の一部であるので否定することが難しい。
自然界においてもこの傾向は顕著だし、柔道競技自体が体重別であることからも明らかである。
例えば地球上の生物の中で最も強いのは、最大かつ最重量の生物であるシロナガスクジラである。
柔道技ってなんだ
じゃあ柔道で言っている技っていったい何なのよ、無意味じゃないかと思うかもしれない。
しかし安心してほしい、ちゃんと意味はあって、効果的に使うこともできる。
結論を言えば、柔道における「技」とは「力や体の使い方」のことである。
何のことはないそれだけのことである。
決して物理法則を無視できるような不思議な力でないことは知っておいてもらいたい。
同時に目的を達成するために、すべての物理法則、生物的な構造を利用することが技である。
優れた技は結果として、まるで魔法のように見えることもあるだけである。
つまりは力や体重は対人的な強さという面でポテンシャルであるといえる。
そして、力や体重の使い方が技であるといえる。
技の例を幾つか挙げてみる、そして技を発動するとは、以下を行うことでもある。
- 自分の強い部分を使い、相手の弱い部分を攻める
- 瞬間的に力を集中させて、相手の緩みや隙をつく
- 瞬間的に相手の力を分散させて弱化する
試合中の柔道選手はものすごいスピードでこれを行っている。
技を修めるには鍛錬が必要
見ていただくとわかる通り、この程度では圧倒的な力の差を埋めることは難しい。
さらに技を知ったからといってすぐに使えるわけではない。
厳しい鍛錬と気の遠くなるような反復練習を経てやっと使えるのが技である。
料理で例えると材料が力や体重、調理方法や調味料が技であるに過ぎない。
食材が良ければ刺身でもおいしいが、食材が悪ければ似ても焼いてもどうにもならないのと似ている。
料理法を試行錯誤しているよりも、良い食材を用意したほうが簡単に美味しい料理が出来上がる。
柔道技名である「巴投げ」や「背負い投げ」などは、技を効率よく発動するためのテンプレートである。
つまりは料理名でありレシピある。
カレーのレシピを知ったからといって、すぐにおいしい料理が作れるとは限らない。
柔道技も同様に巴投げを知ったからといって劇的に強くなるわけではない。
ここが少年漫画による妄想と厳しい現実が大きく異なる点である。
少年漫画においては、主人公は強敵と相対する際、大抵の場合はとても厳しい修行を行う。
そして、必殺技を習得することにより、強敵に勝利する。
しかし、現実にはかめはめ波という必殺技を覚えたからといって、強大な敵に勝てるわけではない。
現実には気の遠くなるような繰り返しの反復練習、試行錯誤が必要であり、最大限まで磨き上げたを両手による掌底打ちをかめはめ波と名付けたに過ぎない。
つまり、柔よく剛を制するためには、力や体重を増すよりもはるかに大きな努力が必要になる。
そのため、単純に強くなるという目的を達成するためには、まずは力や体重を増やすことを推奨する。
具体的には、圧倒的な走り込みと筋力トレーニング、栄養補給を行うことが、最速で強くなるコツだ。
技を具体的に考える
そうはいっても、本ブログは脱力系柔道を目指している。
そのため、筋力トレーニングと並行して頭で理解して効率よく強くなっていこう。
体の使い方という部分で、技の一例を紹介する。
最初に知っておきたいのは、人間の体の中で力の強い部分だ。
具体的には筋肉量が大きい部分、大抵の場合は体重を支えている腰から下と背筋のことである。
特に意識すべきは体を伸ばす筋肉(伸筋)は曲げる筋肉(屈筋)よりも強い。
これは実際に実感できる。
例えば自分と同じ体重のものを持ち上げるのは難しいが、鉄棒にぶら下がることは容易である。
また、伸筋の中でも背筋力はとても大きい、背筋力を測ると100kg近く出せる人も多いだろう。
そして、手よりも脚の方が大きな力を出せるのは想像に難くない。
これらの筋肉を積極的に使うことができれば、効率よく立ち振る舞うことができる。
これを知っていることが重要な要素の一つである。
自分の体を制御する
もう一つ知っておきたいのが、人間は驚くほど自分の体を制御できていないということだ。
自転車や車に乗るのと同じように、体を制御する訓練をすることがとても重要である。
心臓の筋肉など完全に自律している筋肉は省くとして、腕や足、首、腰などは通常自らの意思で動かしている。
ここで、人間は一体どのくらい自分の体を制御できているのかを実際に試してみよう。
まずは以下の動作をして確認してみよう。
- 体育座りをする
- 脱力する
- 手足が伸び、寝転んだ状態になる
- 肘を曲げる
- 脱力する
- 肘が伸びる
それで? だから? あたりまえじゃね? と思うかもしれない。
しかし、重要なのは、脱力すると伸びるという点だ。そう、脱力したのに伸びているのだ
本当に力が入っていないのなら、骨と肉の塊は糸の切れた操り人形のようになるはずだ。
そうならないのは体にテンションが掛かっている、つまりは無意識に筋肉が縮んで作用しているのだ。
脱力という意思に対し、体の屈筋は脱力したが、伸筋がわずかに作用して腕を伸ばしている。
これは多くの人がそうであるので、通常の状態である。
私たちの筋肉は、常に伸ばす力と曲げる力を同時に出している。
そして、腕や上半身については屈筋よりも伸筋の方が制御が難しいということがわかる。
まずこの体の作用を認識し理解することが第一歩である。
- 腕を曲げる=屈筋の力>伸筋の力
- 腕を伸ばす=屈筋の力<伸筋の力
以上は一例であるが、実際は個人差が大きいし、訓練の差もでてくる。
少しずつ自分の体の制御がどうなっているのかを確認していくしかない。
そして、これは自分にしかわからない。
某ハンマー投げの選手は、筋繊維1本1本を知覚できると発言したことがある。
まさに人間の究極系、完全制御であると言える。
力を抜けという指示の実態
柔道の練習や試合で度々言われている「力を抜け」というのがある。
そういわれても、言われたとおりにすると次の瞬間に投げられていることだろう。
力みからの脱力の瞬間は隙でしかないのでそうなるのだが、これについては後に説明しよう。
結果として初心者の試合でよく見かけるのが、ガチガチに組み合って硬直している状態だ。
投げられまいと全身が力み伸筋も屈筋も全力で作用して、打ち消しあい筋肉が硬直している状態だ。
結果としてどちらも動けないので、何も起こらない。
柔道で言うところの力を抜けとは屈筋の力を抜き、伸筋の動きを邪魔しないように動けということである。
伸筋を制御するには伸筋を意識して動かす訓練、すなわち筋力トレーニングとストレッチが必要となる。
スクワット、背筋、懸垂あたりが効果的である。
脱力する意味
脱力すると隙ができるんだから、力んどけばいいじゃないと思うことだろう。
では、続いて脱力する意味を説明しよう。
それは、先述したとおり、力みからの脱力は隙であるが、脱力からの力みは技となるからである。
同じエネルギーでも1秒間に100の力を使うのではなく、0.1秒間に1000の力を集中することができるからである。
わかりやすいように今回も下記の手順で実験してみよう。準備するものは体重計だけだ。バネ式のものがあるとより分かりやすいだろう
- 体重計に乗る
- 100kgの人なら100kgを指す
- スッと膝を曲げる
- 100kgの人でも一瞬100kg以下となる
- グッと動きを止める
- 100kgの人でも一瞬100kg以上となる
- そのまま待つ
- 100kgの人なら100kgを指す
どうだろうか、確認できただろうか。
いつも通り当たり前のことである。体重計が壊れているわけではない。
つまり体重そのものは変わらないが、動くことで瞬間的に地面にかかる荷重は変動していることがわかる。
前述したとおり、体重が軽いほうが不利で体重が重いほうが有利なのである。
- 力み続ける状態は、動かない状態に等しい。
- 力を抜いた瞬間は、荷重を抜いた瞬間に等しい。
- 力を入れた瞬間は、荷重をかけた瞬間に等しい。
どうだろうか、先ほど力を抜いた瞬間に投げられた意味が分かるだろうか。
力を抜いた瞬間は、人は荷重が抜けて軽くなるのだ。つまりは隙が生じる。
逆に力を入れた瞬間は、人は荷重がかかり重くなるのだ。つまりは技を発動できる。
大抵の場合、技の発動前後に技の威力に比例した隙が生じる。これを覚えておこう。
ここまでのことが理解できれば、体重や力がポテンシャルであり、その使い方が技である理由が実感できるだろう。
体重が50kgの人が100kgの人と同じ結果を得るためには2倍近く動かなければならない。
つまり体重が50kgの人は、単純計算で相対的に2倍の隙が生じることになる。
これらの物理法則を利用し、相手に作用させることが技である。
そして、技を効率的に発動させるために脱力する必要があるのだ。
このような小さな技を積み重ねて、相手との差別化を図ることで、初めて「柔よく剛を制する」ことができる。
これには、多くの鍛錬が必要になることは想像に難くない。
今後も脱力系柔道をキーワードに書いていく。
それではまた。
まとめ
- 力と体重がポテンシャル
- 力と体重の使い方が「技」
- 脱力することで生じる「隙」があるから「技」が使える
- 小さな技の積み重ねが「柔よく剛を制す」ことにつながる